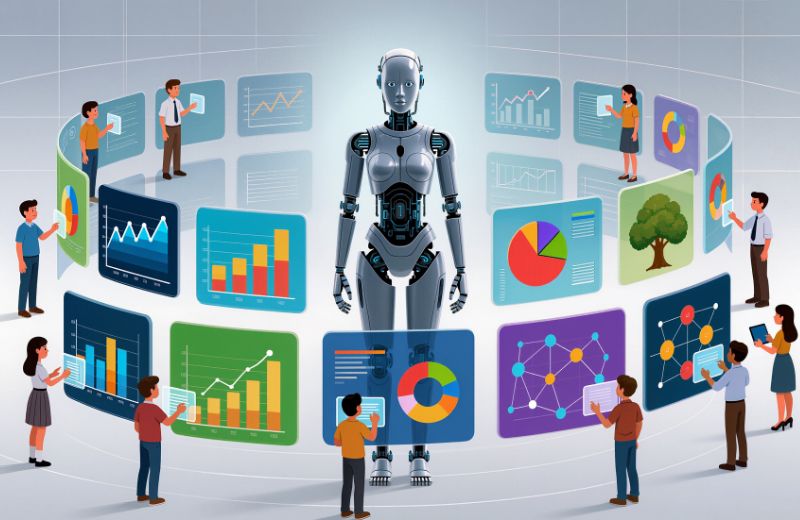2025年岐阜県最低賃金上昇を採用代行(RPO)で乗り越えるコスト上昇
2025年、岐阜県を含む全国の最低賃金が大きく見直されようとしています。中小企業の経営者や採用担当者にとって、この改定は「人材確保のチャンス」と同時に「人件費の圧迫」という二面性を持つ重要なニュースです。特に岐阜県は製造業やサービス業など労働集約型の産業が多く、最低賃金の上昇が経営に直接響きやすい地域でもあります。
「コストが上がるのにどうやって人を採ればいいのか」
「周辺県と比べて、岐阜の賃金水準は有利なのか不利なのか」
「採用活動を効率化して、負担を軽くする方法はないのか」
こんな疑問を持つ経営者や担当者に向け、本記事では2025年の岐阜県最低賃金の改定ポイントを整理し、全国ランキングとの比較や今後の影響を解説します。さらに、コスト上昇にどう対応すべきか、その一つの答えとして「採用代行(RPO)」という外部活用の選択肢を紹介します。
単なる数字の紹介にとどまらず、実務に直結する活用法や導入メリットを具体的に解説していきます。最後までお読みいただければ、最低賃金改定という“避けられない変化”を逆に活かし、自社の採用を強化する戦略が見えてくるはずです。
2025年岐阜県の最低賃金改定と適用時期
まず押さえておきたいのが、岐阜県の最低賃金がどのように改定され、いつから適用されるのかという点です。最低賃金は毎年、厚生労働省の中央最低賃金審議会の答申を受け、各都道府県ごとの地方審議会で議論されたうえで決定されます。
岐阜県の最低賃金は、東海地域の中でも愛知や三重と密接に関連しながら推移してきました。2025年も例外ではなく、地域間のバランスや物価の上昇、労働需給の状況を反映して見直しが行われています。
最低賃金の改定は「単なる金額の変更」ではありません。経営者にとっては人件費計画を修正するタイミングであり、採用担当者にとっては求人条件を見直す重要な分岐点です。特に、新卒採用を考える中小企業では、提示する給与条件が競争力に直結するため、この改定を軽視することはできません。
令和7年の最低賃金答申内容と発効月を確認
令和7年(2025年)の岐阜県最低賃金については、例年どおり夏頃に地方最低賃金審議会から答申が出され、厚生労働省を経て正式に告示されます。その後、10月初旬をめどに新しい最低賃金が発効するのが通例です。
実際の金額水準は、全国的な引き上げ方針と連動します。政府は毎年「地域間格差の是正」と「物価上昇への対応」を掲げ、特に都市部との差を埋めるように地方の最低賃金を引き上げる傾向にあります。岐阜県もその対象となるため、2025年度も前年以上の上昇幅が見込まれています。
ここで重要なのは、「発効月を過ぎた時点で、すべての労働者に対して新しい最低賃金を適用しなければならない」という点です。アルバイトやパートなど雇用形態を問わず対象になるため、経営者は給与システムや雇用契約を見直し、早めに準備を整える必要があります。
例えばこんな対応が求められます
・求人票の賃金条件を新水準に合わせて修正する
・既存従業員の時給を調整し、不公平感が出ないよう配慮する
・採用面接時に提示する条件を再計算し、説明の整合性を確保する
最低賃金改定を「ぎりぎりまで様子を見る」と、直前で求人票の差し替えや従業員対応に追われてしまいます。むしろ早めに答申内容を把握し、戦略的に採用活動へ組み込むことが、中小企業にとってはコスト負担を抑える第一歩になるのです。
全国の地域別最低賃金ランキング一覧
全国の最低賃金は、都道府県ごとに異なり、大きく「都市部」と「地方」で差があります。2025年度もこの傾向は続いており、東京・神奈川・大阪といった大都市圏が最上位に位置し、地方圏との差は依然として存在しています。
例えば、上位の東京都や神奈川県では最低賃金が 1,200円を超える水準 に達する一方で、地方の一部ではまだ 1,000円台前半 にとどまる地域もあります。
この差は単なる統計上の数字にとどまらず、「どの地域に人材が流れやすいか」に直結します。求職者はより高い時給を求めて都市部へ流動する傾向があるため、地方の中小企業は給与条件だけでは競争が難しくなりがちです。
ただし一方で、地域の物価水準や生活コストを踏まえると「地方でも十分生活できる賃金」と受け止められるケースもあります。したがって重要なのは、単純に都市部と比べるのではなく、自社が立地する地域の周辺と比較して有利か不利か を見極めることです。
岐阜県の順位と周辺県との比較情報
では、岐阜県は全国の中でどのあたりに位置しているのでしょうか。2025年の改定後を見据えると、岐阜県の最低賃金は 全国の中位〜やや下位の層 に位置すると予想されます。
特に注目すべきは周辺県との関係です。
・愛知県:東海地方の中心で、製造業やサービス業が集積。岐阜より 数十円高い水準 になるケースが多い。
・三重県:岐阜とやや高め。都市部は愛知に近い求人条件が提示される。
・滋賀県:関西圏に近いため、岐阜と比較してもやや高水準で推移する傾向。
・長野県:地域差が大きく、北信エリアなどは岐阜より低めのこともある。
この比較から見えるのは、岐阜県単独で採用市場を考えるのではなく、愛知・三重・滋賀といった「周辺との競争軸」で採用戦略を立てる必要があるということです。特に岐阜県南部では、名古屋市内まで通勤できる人材が多いため、賃金格差がそのまま人材流出につながりかねません。
一方、岐阜県内の中小企業にとっては、最低賃金が愛知県より低いことで「比較的低コストで人材を雇える」という側面もあります。つまり、周辺県との「差」をうまく活用しながら、賃金以外の魅力(働きやすさ、柔軟なシフト、スキルアップの機会など)を求人に盛り込む工夫 が重要になるのです。
最低賃金の推移と2025年度の改正ポイント
最低賃金は過去数年、毎年のように引き上げられてきました。物価上昇や人手不足といったマクロ要因が背景にあり、今や「最低賃金の上昇」はもはや恒常的な流れと捉えるべき状況です。
2025年度改定では、全国平均で63円アップ(加重平均ベース) という過去最大規模の引き上げが目安として提示されました。
都道府県ごとには、ランク分けがなされ、Aランク・Bランク・Cランクとそれぞれに応じた引き上げ額が定められています。岐阜県はBランクに分類され、64円アップ の答申を受け、発効予定日を 2025年10月18日 としています。
具体的な傾向として、次のようなポイントが見えてきます
・引き上げ幅が全国的に拡大
かつてよりも大きな幅での上昇が見込まれており、地域間格差の是正という政策的な狙いも強く意識されている
・ラング分けと地域ごとの調整
すべての県で同じ引き上げ幅というわけではなく、A~Cランクに分けて、それぞれに応じた目安額が設けられている
・発効時期は10月頃が基本ライン
年度途中や審議遅延を考慮して、改正の告示〜発効は例年10月を中心にずらす地域も存在する
・業種別最低賃金(特定最低賃金)も改定の可能性あり
地域別最低賃金とは別に、特定業種に対応する最低賃金が設けられている場合があり、こちらも改定対象となる(ただし適用時期や範囲は県による)
このような動きを踏まえると、2025年度は「例年以上に改定幅が大きい」「事前準備を怠れば混乱しやすい」年になると予想できます。
労働者・企業に与える影響とは?
最低賃金の引き上げは、労働者と企業双方に波及影響をもたらします。ただし、影響は業種・規模・地域によって異なります。あなたの企業にとってどのような影響があり得るかを整理しておきましょう。
労働者側への影響
- 賃金アップ・収入底上げ
とくに時給制で働くパート・アルバイト・派遣社員にとって、最低賃金の引き上げは直接的に手取りを底上げすることになります。生活の安定につながる面があります。 - 労働意欲・転職意向の変化
他の企業・地域の時給差が狭まれば、より条件の良い職場への流動性が高まる可能性があります。「賃金以外の価値」が応募先選定の要因として重視されやすくなるでしょう。 - 社会保険・扶養ラインへの影響
賃金が上がることで、パート・アルバイトの報酬が扶養範囲を超えるケースも増えます。たとえば「106万円の壁」に関わる可能性が出てくるため、当該従業員との調整や説明が必要です。
企業側への影響
- 人件費の上昇
避けられない影響として、全体的な人件費が増加します。特に時給ベースでの業務が多い企業や、非正規従業員比率の高い業態ではその影響が顕著です。 - 既存従業員との給与バランス調整
新しい最低賃金水準を基準にしなければならないため、既存スタッフの時給・月給構成を見直す必要が出てきます。バランスを崩さないように設計しないと、内部不満や離職リスクも生じ得ます。 - 求人条件の再設計
採用活動中、求人票に記載されている賃金が旧基準のままだと応募者から見劣りする可能性があります。改定後は求人情報をすみやかに修正しないと、採用の競争力が低下します。 - 採算性への圧迫
原価率を上げにくい事業や、価格転嫁が難しいビジネスモデルを持つ企業では利益を圧迫されるリスクがあります。 - 対策コスト・対応リスク
最低賃金引き上げに備えて、業務プロセス見直し、システム改修、研修強化などの初期投資が必要になる場合があります。また、法令違反のリスクを軽減するための法務・労務体制の整備も求められます。
中小企業の採用活動と最低賃金の関係
最低賃金の上昇は、人件費そのものだけでなく、採用活動の在り方 にも直結します。求人を出す際、時給や初任給は最低賃金を下回ることができません。つまり改定が行われると、それに合わせて求人条件の底上げが必須となります。
特に中小企業では、次のような課題が発生しやすいです。
・求人票の修正コスト
最低賃金改定のたびに、ハローワークや求人媒体の条件を差し替えなければならない。
・競争激化
同じエリアで他社も一斉に条件を見直すため、採用市場では「賃金以外の魅力」で差別化しないと埋もれてしまう。
・内部バランス調整
新しく採用する人の時給を上げると、既存従業員との賃金格差が問題になりやすい。
・長期的な人件費圧迫
一度引き上げた給与水準は下げにくいため、採用計画の見直しが必要になる。
このように最低賃金の上昇は「採用の入り口コスト」を押し上げ、中小企業の経営にじわじわと負担を与えるのです。
採用コストの増加と採用代行(RPO)の選択肢
そこで注目されるのが RPO(Recruitment Process Outsourcing)=採用代行 という手法です。これは、採用に関わる業務の一部または全部を外部の専門会社に委託する仕組みのこと。最低賃金が上がり、採用コストが増す時代において、経営資源を効率的に活用できる選択肢として広がりつつあります。
採用代行を使うメリット
- 採用単価を下げられる
求人広告を闇雲に増やすのではなく、効果的な媒体選定や応募者管理を任せることで、1人当たりの採用コストを抑えられる。 - 人件費の固定化を防げる
自社で専任の採用担当を増員するより、必要な時期だけ外注する方が柔軟。 - 専門ノウハウの活用
応募者対応や面接日程調整など、時間がかかる業務を効率的に処理できる。特に新卒採用は応募数が多いため効果が大きい。 - 採用スピードの向上
社内だけで進めるより、短期間で母集団形成から内定までの流れを作れる。
中小企業にとっての意義
最低賃金が上がると、どうしても「人件費=コスト」という発想になりがちです。しかし、採用代行を活用することで、人件費の増加を“投資”に変える仕組みを構築できます。
たとえば、外注で応募者管理を任せることで、経営者や人事担当者は「自社の魅力をどう伝えるか」「採用した人材をどう育成するか」といった本質的な部分に集中できるようになります。結果的に、採用効率だけでなく定着率の改善にもつながります。
RPO(採用代行)とは?仕組みと導入のメリット
RPO(Recruitment Process Outsourcing)は、採用活動の一部または全体を外部の専門会社に委託する仕組みです。近年、最低賃金の上昇や採用市場の競争激化を背景に、大手企業だけでなく中小企業にも導入が広がっています。
仕組み
RPOの仕組みはシンプルです。求人媒体の選定・応募者対応・面接調整・内定通知といった「採用に必要な業務」を外部に任せることで、社内のリソースを節約します。完全に丸ごと委託するケースもあれば、一部の工程だけをアウトソースするハイブリッド型もあります。
メリット
- 採用コストの最適化
求人広告を闇雲に出すより、外部のノウハウを活用することで効率的な集客が可能。結果的に採用単価を抑えられる。 - 採用スピードの向上
応募者対応や面接日程調整に時間を割かずに済み、選考スピードが早まる。人材が他社に流れる前に確保できる。 - 専門知識・データの活用
人材市場や各種媒体の最新トレンドに精通した担当者がサポートしてくれるため、自社だけでは得られない情報が得られる。 - 採用担当者の負担軽減
日常業務と並行して採用業務を進める中小企業にとって、時間的な負担が減ることは大きなメリット。
RPOを導入することで、最低賃金上昇によるコスト圧力を「採用効率化」という形で相殺できるのです。
採用業務外注の具体的な方法と相談の進め方
では、実際にRPOを導入するときはどのように進めればよいのでしょうか。
1. 外注範囲を決める
・母集団形成だけ依頼(求人広告の選定や応募管理など)
・面接調整や候補者対応のみ委託
・フルパッケージで丸ごと任せる
自社の課題が「応募者が集まらない」のか、「面接調整に追われる」のかによって依頼範囲を絞るのがポイントです。
2. 費用のイメージを把握する
RPOの料金体系は「固定費型」と「成果報酬型」に大別されます。
・固定費型:月額制で一定額を支払う。安定的に採用したい場合に向く。
・成果報酬型:採用人数に応じて費用が発生。採用数が少ない企業でも利用しやすい。
3. パートナー企業を選ぶ
信頼できるRPO会社を見つけるには、以下の観点が重要です。
・自社と同じ規模・業種での実績があるか
・地域の求人市場に詳しいか
・対応スピードや柔軟性があるか
4. 相談の進め方
初回の相談では「どのポジションを採用したいか」「年間で何名を予定しているか」「どんな課題があるか」を整理して伝えるとスムーズです。これにより、外注範囲・費用・スケジュールが明確になります。
RPOは「コスト削減のための仕組み」ではなく、むしろ “限られた人材獲得の機会を逃さないための投資” として活用すべきものです。最低賃金が上昇し続ける時代だからこそ、戦略的な採用の選択肢として注目すべき方法だと言えるでしょう。

岐阜県最低賃金への対応と今後の採用戦略
2025年度の最低賃金改定は、過去最大規模の引き上げとなり、岐阜県をはじめ全国の中小企業に少なからぬ影響を及ぼします。人件費増加は避けられない現実ですが、その一方で「採用条件の底上げにより人材確保のチャンスが広がる」という側面もあります。
本記事で取り上げたポイントを整理すると、次の3点に集約できます。
- 最低賃金改定を正しく把握すること
適用時期や引き上げ額をいち早く確認し、給与体系や求人条件を整えることが必須です。後手に回ると、採用市場での競争力を失いかねません。 - 地域比較を踏まえた戦略設計
岐阜県単独で見るのではなく、愛知・三重・滋賀など周辺地域の賃金水準も意識する必要があります。人材は県境を越えて動くため、広い視野で採用条件を考えることが大切です。 - 採用代行(RPO)の活用で効率化を図る
最低賃金上昇に伴うコスト増を「採用業務の効率化」で相殺する。求人媒体の選定や応募者管理、面接調整といった業務を外部に委託することで、コスト削減と採用スピード向上の両立が可能です。
最低賃金は今後も引き上げが続くと予想されます。つまり中小企業にとって、これからの採用活動は「人件費増加をいかに戦略的に乗り越えるか」が最大のテーマになります。
賃金条件だけで戦うのではなく、働きやすさ・成長機会・柔軟な働き方 といった“非金銭的な魅力”をアピールすることも重要です。そして採用活動そのものの効率化や外部リソース活用を組み合わせることで、人材確保と経営の安定を両立させることができます。
最低賃金上昇を「リスク」と捉えるか、「改革のきっかけ」と捉えるかは、経営者次第です。2025年はまさに、その転換点の年。今こそ自社の採用戦略を見直し、未来に備えるタイミングなのです。